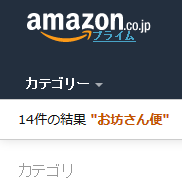Amazonがついにお坊さんを出前!?!?
昨日、衝撃的なニュースが業界を駆け巡りました。
Amazonから、お坊さんの手配をできるというのです。しかも手頃な値段で。
ついにこの葬儀業界にも黒船がやってきたか、、、これは日本のお寺も葬儀屋もいよいよグローバル社会に放り込まれることになるのか。。。
ていうか、坊さんが段ボールで家に届けられるの・・・???
その名も「お坊さん便」値段も手ごろな35,000円から
噂のお坊さん宅配サービスの名は「お坊さん便」、本日12月8日からAmazonでの提供が始まりました。
先ほどより「Amazonで宅配!」などと連呼してしまいましたが、正確には、こちらはAmazonマーケットプレイスの商品、つまり、Amazonで買うことができるものの、販売元は「株式会社みんれび」という会社。
注文すると、こちらの会社でお坊さんを手配して派遣してくれる、ということなんですね。
実はこの「みんれび」という会社、ネットで、お葬式や墓石、永代供養墓のみならず、海洋散骨、宇宙葬まで、非常にリーズナブルな価格で販売している業界の革命児であります。
当サイトでも以前、永代供養墓の価格競争が激化している件の記事の中で、永代供養墓をなんと35000円ぽっきりで提供している会社、ということで取り上げたことがあります。
みんれびは、以前から低価格の葬祭系サービスを提供しており、じつはこの「お坊さん便」も、既に2年半以上前、2013年5月にリリースされたサービスでした。
なんと2014年時点で問い合わせ件数は約8000件、年間受注件数が前年比3倍、ということで、Amazonに出店し、さらなるサービスの拡大に出たものと思われます。
さて、この「お坊さん便」、料金は先にも述べたとおり何と35000円。自宅と墓など2か所で読経する場合、戒名の授与がある場合はオプションだが、両方頼んでも全部で65000円、非常に分かりやすくシンプルな料金体系となっています。
そして利用方法は、以下の通り。
1、Amazonで注文
↓
2、法事法要の希望日時、場所、宗派をメールで伝える(9:00~21:00/年中無休)
↓
3、僧侶の手配情報を記載した書面(チケット)が郵送される
↓
4、詳しい法事法要を僧侶と電話で打合せ
↓
5、法事法要の読経
と、基本的にはメールと電話ですべて済んでしまいますね。
お寺とあまり付き合いがない、お寺との話がわずらわしい、という方には非常に使いやすくありがたいサービスと言って間違いないでしょう。
ネットでも飛び交う賛否両論
このサービスのリリースを受けて、ネット上でも様々な意見が飛び交っています。
「檀家離れが問題になってるから時間契約でもきっちり時給発生してるし坊さん側もありがたいのでは?」
「利用者にとって便利なサービスだが、寺院経営をする側は苦しいところ。寺院経営がさらに厳しくなる。」
などと、寺院側の問題を取り上げる冷静な意見もある一方、
「そこまでしてお経が必要か?」
「信仰も何もあったもんじゃない」
「普段信仰してないなら別に必要ないのでは?」
という完全否定的な意見も結構多い。
だが、実は一番多いのは、
「すげぇ時代が来た」
「便利かもしれんが寂しいな」
「ありがたみもへったくれも無いが、まぁ時代なんだろうね。」
「便利ではあるが、「なんだかなぁ~」という感じもします。」
「親族の自己満足としては必要だが」
といった、好きではないけど受け入れるべきなんだろう、という諦めにも似た気持ちを吐露したコメントでした。
全面的に肯定している意見というのはほとんど見当たりません。
もちろん、「待ってました、こんなサービス!」と思ってもおおっぴらには言いづらいでしょうが、どうやら小さくない需要があるようです。
そもそもこういったサービスができた背景には、どういう時代の流れがあるのでしょうか?
寺院の経済状況は苦しい!?

近年、大規模な有名寺院を除けば、その経済状況は非常に厳しくなっています。
小規模な寺院とくに地方では、檀家の減少に歯止めがかからず、住職が常駐していないところもざらにあるそうです。寺院が、専業でやっていくためには、最低200件の檀家が必要だと言われています。
しかし、若年層の檀家離れ、高齢信者の死亡、信者の都市への移住など、檀家減少の要因には事欠かない今、檀家の確保は非常に困難な課題です。
都市部でも、人口の減少こそないものの、新たな檀家の獲得は非常に難しいことには変わりありません。
このような状況下、墓地を新たに設けたり、永代供養の施設を建立したりしてその販売収益や管理収益を得ることで収益源を確保している寺院もありますが、そんな土地も財力もない寺院の住職は、副業をするしかありません。
今や兼業住職は全体の5割以上、寺院の約45%がなんと年収300万円以下だという説もあります。
この「お坊さん便」で派遣されるお坊さんが、みなそのような状況とは限りませんが、例え知らないお客さん、1回きり、安めのお布施であっても、1件でも多くのお客さんが欲しい、そういうお坊さん側の需要があることは間違いないでしょう。
もちろん、こういうサービスによって、通常5万~10万くらいとも言われるお布施の相場が崩れてしまう可能性もあるわけですが、そうも言っていられないのです。
頼む側の事情とは

一方、「お坊さん便」のような手軽すぎるようにも見えるライトなサービスを利用するお客さんにはどのような事情があるのでしょうか。
(以下、弊社調査の内容であり、「お坊さん便」利用者の意見ではありません。)
● 檀家となっており、檀家として活動している人(またはそれに近い付き合いのある寺がある)は、ライトなサービスを頼まない
⇒檀家となっている以上、原則的に葬祭活動を自分のお寺以外に頼むということはありません。村八分にさえなりかねないからです。
● 檀家になってはいないが信心深い人は、ライトなサービスを頼まない
⇒こういう人は、自分が葬祭をお願いしたいお寺があるので、どこのお寺さんが来るかわからないサービスは頼みません。
● 檀家にもなっていないし、信心深くもない人は、ライトなサービスを頼まない
⇒特に読経してもらう必要がないからです。
…では、どのような人がライトなサービスを頼みうるのか。
そう、檀家だが信心深くない人、というのが抜けていますね。
実は、上で述べた、ネット上の「親族の自己満足としては必要だが」という意見が非常に言い得ています。
世代による決定的な宗教への意識の違い
お寺は70年前、第二次世界大戦が終わるまでは、広大な田畑や山林を有する地主でもありました。したがってそこには多くの小作人がおり、莫大な収入もありました。その代わり、お寺は集落のお祭りを行ったり、葬祭を行ったり、お墓の管理をしたり、いわゆる互助会的な組織としても大きな役割を持っていたのです。
従って、この時代を知っている人にとって、お寺というのは信仰の対象であるだけでなく、集落の中心として生活から切っても切り離せないものでした。
ところが、第二次世界大戦が終わると、GHQの主導で農地改革が行われ、農地はタダ同然で地主から買い上げられたうえ、小作人に売り渡されました。
これにより、お寺は収益源の大部分を失うとともに、近隣住民との関係も急速に薄れていったのです。
折しも、程なく高度成長期が到来、多くの人々が地方から都市部へ移動し、お寺・宗教とは無縁な生活を送るようになりました。
これによって、戦前のお寺を知る人、だいたい80代以上の世代と、70代以下の世代では(都会と農村など地域差などもかなりありますが)、宗教観がかなり違う、という状況に必然的になってしまったわけです。
仮にその戦前のお寺を知る世代をお寺世代、そうでない世代を都会世代としましょう。
今はまさに、お寺世代の人が亡くなり、その子である都会世代が葬祭・法要を執り行う、というケースが非常に多くなっている時代なのです。
お寺世代では、法要はもちろん毎日のお勤めも欠かさず、檀家としてもお寺に毎年10~20万以上のお金を払ってきた人は大勢います。
半面、都会世代は、親がお寺にお世話になってきたことは認識しつつも、お布施が高すぎるのでは、と思っている人もいて、そういう人は、親が亡くなったのを機にお寺との付き合いを減らしたり、檀家を辞めたり、という選択をすることになるのです。(もっとも、自分は親の死を機に法要などはすっぱりやめてしまいたい、と思っても、親の兄弟・親族や、あるいは地方だと「本家」などの反対にあって、そういった親戚への体面上やめることができないケースも多いと聞きますが。)
信心深かった親だったし、3回忌や7回忌など節目にはお経くらいは読んであげないと、そういう意識を持っている人は多いのです。
そのような場合、贅沢はせず、なるべくシンプルに済ませたい、という結論にもなるわけです。
このような世代間の意識の差が、一見軽くも見えてしまう法要サービスを、まさに必要としているのではないでしょうか。
宗教活動?営利活動?
Amazonのような商業サイトで営利的宗教活動の宣伝をする以上、これは宗教活動ではなく、営利活動ではないのか?という問題も出てきます。
先日、赤坂の納骨堂が、宗教施設であるにもかかわらず、販売を一般企業に丸投げしていたことから営利活動のための施設だとして、東京都から固定資産税を請求され、裁判になっている、というニュースがあったばかり。(通常宗教施設に固定資産税は課税されないため。)
宗教活動?営利活動?という問題は、表面的にどちらだと判断するには根深すぎる問題です。この記事で述べた、寺院の経済状況や、寺院の歴史を踏まえ、これからの我々一般人とお寺との関係性をどうするのか、またお寺をどうやって残していくのか、ということを考えなければ何も解決できません。
これについては、また改めて別稿でお伝えしたいと思います。
<追記>
その後12月24日、全日本仏教会は公式ホームページにおいて声明を発表しました。
⇒”「Amazonのお坊さん便 僧侶手配サービス」について”全日本仏教会
この声明、「お坊さん便」の中止を求めているかと思いきや、よくよく読んでみると、
これには、・・(中略)・・ 仏教界からは宗教をビジネス化しているという批判が起こっています。
・・・世界的な規模で事業を展開する「Amazon」の、宗教に対する姿勢に疑問と失望を禁じ得ません。しっかりと対応していきたいと考えます。
と、中止を求めているわけでもなく、どのような対応をするのかも明らかにされていません。
また、「Amazon」に対しては失望を投げかけているものの、運営者の「みんれび」には何ら触れてさえいないのです。
ここに、全日本仏教会の苦しい立場が凝縮されているのではないでしょうか。
この「お坊さん便」、当のお坊さんの間でも賛否が分かれているようです。ただ、仏教会の声明にもある
お布施は、サービスの対価ではありません。・・(略)・・慈悲の心をもって他人に財施などを施す・・(略)・・修行の一つです。
ということについては、どのお坊さんも同じ考えであるようです。
サービス対価ではないからこそのありがたみがある、いくらか分からない面倒さにありがたさを感じる人もいる、というのも事実であるようです。
一方で、檀家離れによるお寺の収支の悪化、宗教心の低下はあるものの形は整えたい市民の増加は、間違いなく「お坊さん便」のようなひとまとめ定額制のサービスの需要を増やしています。
「お坊さん便」のデメリットとして、「どんなお坊さんが来るかわからない」というものがありますが、一定数の人にはそれさえ求められていない(つまりお坊さんであればどんな人であれ構わない)可能性さえあるのです。
「お坊さん便」は、その後もAmazonで継続して販売されています。
今後、全日本仏教会がどのような対応をするのか、あるいはしないのか、気になるところです。