2018年の大河ドラマ「西郷どん(せごどん)」、主人公の西郷隆盛(吉之助)が南国薩摩(鹿児島県)から明治維新を成し遂げる物語。
序盤・中盤の舞台は薩摩ですが、明治維新を成し遂げた後、西郷隆盛や大久保利通をはじめ、多くの薩摩人たちは新政府の要人として拠点を東京に移します。
しかし、明治六年政変で隆盛は官職を追われ薩摩に、そして1877年に起こった西南戦争では、西郷と大久保が敵味方に分かれて戦うという悲劇的な結末を迎えます。
薩摩軍の西郷方についた人達は、西郷隆盛含め、その後多くが鹿児島に葬られています。
一方、新政府軍で戦った人は、その後も政府の要人として活躍し、東京で葬られている人が多くいます。
都立青山霊園は、その東京で生涯を終えた人々が多く眠る墓地の一つ。
青山霊園で西郷どんゆかりの人々のお墓を巡ってみましょう。
青山霊園に眠る西郷どんの仲間達
今回は青山霊園の南端、南中央入口に近いところより、北(青山一丁目方面)に向かう順番でご案内します。
南中央入口は、電車だと東京メトロ千代田線乃木坂駅5番出口より徒歩約6分、日比谷線六本木駅2番出口から徒歩約10分です。
西郷 糸子(隆盛の3人目の妻・寅太郎の母)
西郷 寅太郎(隆盛・糸子の長男、侯爵)
【位置:1種イ11号22側】
(さいごう いとこ、1843-1922)
(さいごう とらたろう、1866-1919)
授かりもした♡#大河ドラマ #西郷どん#鈴木亮平 #吉之助#黒木華 #糸#ほんのこっか亮平どん?#幸せそうじゃっでどっちでもよか#まっこておめでとうございもす pic.twitter.com/kZuEgrAGWA
— 大河ドラマ「西郷どん」 (@nhk_segodon) 2018年9月4日
糸子(「イト」とも。「西郷どん」では糸。)は、西郷隆盛の3番目の妻。数え23歳のときの結婚でしたが、糸子も再婚でした。
隆盛との間には寅太郎、牛二郎、酉三の3人の子供があり、隆盛の島妻である愛加那との子である菊次郎・菊も引き取り育てました。
明るい性格で、隆盛とは非常に仲が良かったそうです。
上野公園に西郷隆盛の銅像ができたとき、それを見て「こげなお人じゃなかった…」と大声で叫んでしまった、というのは有名なエピソードです。
寅太郎は隆盛とイトの間に生まれた長男。
西南戦争で隆盛が敗死したことにより、寅太郎は糸子とともに薩摩で不遇をかこっていました。
1884年、勝海舟などの取り成しによってドイツに留学、帰国後陸軍少尉となりました。
その後貴族院議員、東京俘虜収容所長を務めるなど活躍、侯爵に任ぜられました。
1919年、肺炎により52歳の若さで亡くなりました。
青山霊園では、イトと、息子の寅太郎・牛次郎・酉三の4人の石碑が並んでいます。
川路 利良
【位置:1種イ4号1側】
(かわじ としよし 1834年6月17日~1879年10月13日)
西郷親衛隊でごわす!#大河ドラマ #西郷どん#泉澤祐希 #川路利良#大野拓朗 #中村半次郎#堀井新太 #村田新八 pic.twitter.com/UP6Ls7YaVs
— 大河ドラマ「西郷どん」 (@nhk_segodon) 2018年8月17日
西郷どんではまだ影の薄い川路ですが、禁門の変で長州藩遊撃隊総督の来島又兵衛(大河ドラマでは長州力が演じていた敵方大将)を狙撃して倒すという戦功を挙げています。
明治維新後は、隆盛の招きで東京府大属となります。
その後、西欧視察団の一員として欧州各国の警察を視察、帰国後、日本の近代警察制度を確立し初代大警視(現在でいう警視総監)に就任しました。
明治六年政変で隆盛が下野し薩摩出身者の多くが従った際も、川路は「私情においてはまことに忍びないが、国家行政の活動は一日として休むことは許されない。」と引き続き国務に身を捧げ続けました。
激務がたたったか、満45歳の若さで命を落としますが、「日本警察の父」として、その業績は再評価されています。
川路利良の墓は、利良の墓のほか、一族の墓碑が並ぶかなり立派なお墓です。
中心には「大警視川路利良」の偉業を称える3メートルを超えるほどの大きな碑も立っています。
大久保 利通(正助・一蔵)
大久保 満寿子(増子)(利通の妻)
【位置:1種イ2号】
(おおくぼ としみち 1830年9月26日~1878年5月14日)
(おおくぼ ますこ 不詳 – 1878年12月7日)
正助の心はすーっかりお見通し。
まっこてよか嫁をもろうたなぁ〜。
#大河ドラマ #西郷どん#美村里江 #満寿 pic.twitter.com/Xc9GJunEiW— 大河ドラマ「西郷どん」 (@nhk_segodon) 2018年4月11日
隆盛の一番の親友でもある利通は、隆盛と共に明治維新を成し遂げます。
しかし、新政府ではしばしば隆盛と意見が合わず、征韓論での対立が引き金となって隆盛は官職を辞して鹿児島に戻ってしまいます。(明治六年政変)
隆盛が去った後も新政府のリーダー格として新しい日本の再建に尽力していた利通ですが、西南戦争ではついに隆盛と敵対し戦うことになってしまいます。
隆盛の死を知った利通は、周りを憚ることもなく号泣したと言われます。
そのわずか8か月後、利通は新政府に不満をもった士族に襲われ、不慮の死を遂げます。
西郷どんの敵となった利通は鹿児島人から非常に嫌われることとなってしまい、お骨は鹿児島に戻ることもできなかったと言いますが、青山霊園のお墓は広い霊園でも随一の威容を誇っています。
入口には鳥居が立ち、あたかも大久保神社のような様相を呈しています。
明治維新、一の功を打ち立てた利通の業績を感じられるお墓です。
利通の偉業を常に陰から支え続け、また利通との間に5人の子をもうけました。
利通が暗殺されると体調を崩し、その死のわずか半年後、後を追うように亡くなります。
お墓は、利通の墓と向き合うように、少し離れたところに立っています。
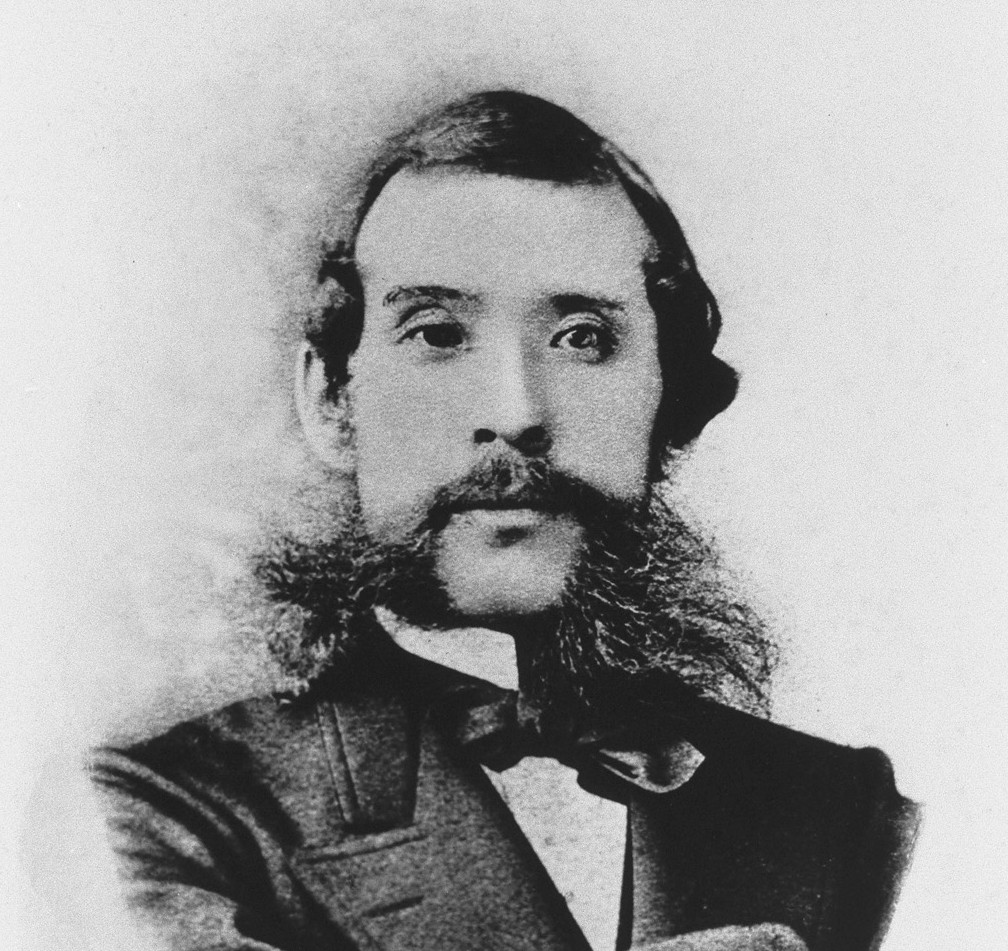
故郷に戻ることができなかった近代日本建国の父大久保利通の墓(政治家・1878年5月14日没・青山霊園)
海江田 信義(有村俊斎・海江田武次)
【位置:1種ロ12号9側】
(かいえだ のぶよし 1832年3月13日~1906年10月27日)
見た目はボロでも
心は錦じゃ!#大河ドラマ #西郷どん#高橋光臣 #有村俊斎 pic.twitter.com/186Ng6d0dA— 大河ドラマ「西郷どん」 (@nhk_segodon) 2018年5月11日
西郷どんでは、少しおっちょこちょいだが西郷を慕う熱い男というキャラ。
史実では、西郷よりも島津久光や大久保に評価され近い関係にあったようです。
明治維新後は奈良県知事を勤めたあと、元老院議官・貴族院議員・枢密顧問官などで活躍しました。
明治六年政変のときは政府の中枢におらず、西南戦争にも参加しませんでした。
亡くなったのは明治39年(1906年)で享年満74歳。精忠組では一番長生きし、西郷や大久保の死を悼んだと言います。
信義の長女テツは東郷平八郎と結婚しているほか、妹も東郷家に嫁ぐなど、元薩摩藩士の東郷家とは縁深くつながっています。
お墓は、溶岩のような土台の上に石碑が乗ったような形。
故郷の桜島をイメージしたものかもしれません。
有村 雄助・次左衛門
【位置:1種ロ12号9側】
(ありむら ゆうすけ 1835年~1860年4月14日)
(ありむら じざえもん 1839年2月11日~1860年3月24日)
ドラマ「西郷どん」では次左衛門がわずかに登場するのみですが、海江田信義(有村俊斎)には、有村雄助と有村次左衛門という二人の弟がいました。
二人は薩摩藩を脱藩し、江戸で水戸藩士らと共に尊攘活動を行うなどやや過激な活動をしていました。
1859年井伊直弼による安政の大獄が起きると、井伊の暗殺を計画します。
計画は桜田門外の変として決行され、次左衛門は井伊の駕籠を襲いその首を取りますが、井伊の供回りに斬られ命を落とします。
襲撃には参加しなかった雄助も首謀者の一人として幕府に追われる立場となり、一旦は薩摩藩に匿われたものの藩命により自害しました。
明治維新よりかなり前に、しかも低い身分のまま命を落とした二人ですが、青山霊園にお墓が立てられたのは、桜田門外の変での活動が後世評価されたものと言えるでしょう。
永田 熊吉
【位置:1種ロ21号11側】
(ながた くまきち 1835年不詳~1900年12月25日)
「熊吉、ここまであいがとなぁ」とねぎらう若さぁ。
と、なぜか嫉妬する桐野さぁ。#大河ドラマ #西郷どん#塚地武雅 #熊吉#鈴木亮平 #西郷隆盛#大野拓朗 #桐野利秋 #西郷先生愛が止まりもはん pic.twitter.com/zqv9uQXZPt— 大河ドラマ「西郷どん」 (@nhk_segodon) 2018年12月13日
永田家は父の代より使用人として西郷家に仕えており、熊吉も西郷家に仕え、家事などを取り仕切っていたと言います。
大河ドラマでは吉之助よりかなり年上の設定になっていますが、実際には7歳ほど年下です。
戊辰戦争では吉之助に同行、明治維新後は東京の西郷邸に住み、西郷が明治6年政変で官職を辞し鹿児島へ戻ると、東京の屋敷の処分などを行い共に鹿児島へ戻りました。
西南戦争では吉之助に従軍するも、吉之助の息子菊次郎を託され、共に弟従道に投稿しました。
吉之助が亡くなった後しばらくは鹿児島で西郷家に仕えていたものの、明治19年(1886年)には西郷従道に呼ばれて再び東京へ。以降亡くなるまで、目黒の西郷従道邸に住み西郷邸の管理や庭師などをしました。
従道邸跡である現在の西郷山公園や菅刈公園の原形を作ったのは熊吉とも言われています。
西郷家に尽くし、また西郷家の人からも家族同様に頼られるなど、西郷家とともに過ごした生涯でした。
青山霊園に眠るその他の人々
青山霊園は、明治期の有名人のお墓が多く、特に薩摩藩士や明治維新に関わった人については多くのお墓があります。
| 位置 | 略歴 | |
| 吉井 友実 | 1種イ6号4側 | 薩摩藩士。維新後は日本鉄道社長として鉄道普及に尽力。 |
| 黒田 清隆 | 1種イ4号13側 | 薩摩藩士。薩長同盟に大きく貢献した。後に第2代内閣総理大臣。 |
| 松方 正義 | 1種ロ17号1側 | 薩摩藩士。幕末期から活躍するが、松方財政など明治以降の功績が有名。内閣総理大臣も務める。 |
| 後藤 象二郎 | 1種イ13号24側 | 土佐藩士。大政奉還に貢献。明治六年政変で下野し以後実業家として活躍。 |
| 牧野 伸顕 | 1種ロ12号 | 大久保利通の次男。政治家として外務大臣など歴任。麻生太郎は曾孫にあたる。 |
| 湯地 定基 | 1種イ3号3側 | 薩摩藩士。明治から昭和期の開拓使・内務官僚、元老院議官、貴族院勅選議員。 |
| 黒田 清隆 | 1種イ4号13側他 | 薩摩藩士。戊辰戦争・西南戦争でも活躍。第2代内閣総理大臣。 |
| 野津 鎮雄 | 1種イ1号26側 | 薩摩藩士。薩英戦争、戊辰戦争で活躍。後に帝国陸軍中将。 |
| 野津 道貫 | 1種イ1号26側 | 薩摩藩士。鎮雄の弟。戊辰戦争以降軍人として活躍。後に元帥陸軍大将。 |
| 樺山 資雄 | 1種イ10号9側 | 薩摩藩士。明治期官僚として活躍。妻・直子の母は大久保利通の母の実妹。 |
| 樺山 資英 | 1種ロ12号 | 資雄の次男。貴族院議員。 |
他にも、青山霊園には明治期の偉人を中心に有名な人のお墓があります。

青山霊園に眠る有名人・著名人(幕末の志士ほか政治家が多数。忠犬の碑も)
なお、西郷イトの墓から大久保利通のお墓までは、まっすぐ歩いて10分以上の距離があります。
途中にベンチなども多く設置されていますので、十分休みながら、散策を楽しみましょう。
東京の他の墓地に眠る西郷どんの登場人物
| 墓所 | 略歴 | |
| 西郷 従道(信吾) | 多磨霊園 | 隆盛の弟。明治政府の重鎮として活躍。 |
| 岩倉 具視 | 品川区 海晏寺 | 下級公家の出ながら、明治維新の中心人物として活躍。 |
| 徳川(一橋) 慶喜 | 谷中霊園 | 江戸幕府最後の将軍。 |
| 篤姫(天璋院) | 台東区 上野寛永寺 | 島津斉彬養女で13代将軍家定の正室。江戸城無血開城に尽力。 |
| 勝 海舟 | 大田区 洗足池公園 | 末期江戸幕府の海軍のトップとなり開国を推進。江戸城無血開城を成し遂げた。 |
| 山岡 鉄舟(鉄太郎) | 台東区 全生庵 | 幕臣として敵方西郷の下へ単身赴き、江戸城無血開城に大きく貢献した。 |
| 阿部 正弘 | 谷中霊園 | 薩摩と縁が深い、江戸幕府老中。 |
| 井伊 直弼 | 世田谷区 豪徳寺 | 桜田門外の変で撃たれた江戸幕府大老。 |

井伊直弼の墓(豪徳寺) – 桜田門外の変で殺害され悪役となった大老
東京以外の墓地に眠る西郷どんの登場人物
| 墓所 | 略歴 | |
| 西郷 隆盛(吉之助) | 鹿児島 南洲墓地 | |
| 西郷 吉二郎 | 上越市 会津墓地 | 隆盛のいない西郷家を支えた。戊辰戦争で死去。 |
| 小松 帯刀(清廉) | 鹿児島 園林寺跡 | 隆盛の上司で明治維新の立役者の一人。新政府でも活躍が期待されたが若くして死去。 |
| 大山 格之助(綱良) | 鹿児島 南洲墓地 | 精忠組の一人。西南戦争では隆盛を支える。 |
| 村田 新八 | 鹿児島 南洲墓地 | 西南戦争で自決。 |
| 中村 半次郎(桐野 利秋) | 鹿児島 南洲墓地 | 人斬り半次郎。西南戦争で討死。 |
| 桂 小五郎(木戸孝允) | 京都霊山護国神社 | 長州藩士。維新の三傑。 |
| 坂本 龍馬 | 京都霊山護国神社 | 海援隊創始者。 |
| 坂本 りょう(おりょう) | 横須賀市 信楽寺 | 龍馬の妻。再婚後「西村ツル」となり横須賀で過ごした。 |

都立霊園に眠る有名人・著名人(政治家・軍人・芸能人・芸術家など)

大谿山 豪徳寺(招き猫発祥の寺)















